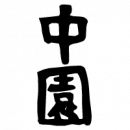前回と前々回の2回にわたり、セクキャバのオーナーKさんに誘われてデリヘルの開業にたずさわった話をご紹介しました。
今回は、そのKさんが経営していたセクキャバ『R』(仮名)での出来事を綴ってみようと思います。私は酒屋の配達員として納品に行っていただけで、客として利用したことはなかったのですが、納品業者だったからこそ知り得た裏話を、少しだけご紹介してみます。
女の子たちの会話
私が勤めていた酒屋は実店舗とはべつに歓楽街の一角に配達所を構えていて、注文を受けるとすぐに配達に向かえるような態勢をとっていました。
その日、定時の22時に配達所を閉めると、先輩従業員と別れ、セクキャバ『R』へ向かいました。その頃、私は仕事終わりに一息つきに『R』へ行くことがよくあったのです。
『R』は歓楽街の大きなレジャービルの中にあり、店前の廊下には待合用の長いソファー、棚に漫画や雑誌が並んでいるだけでなく、客が待ち時間をつぶせるように2台のスロットマシンまで置かれてありました。
その日は、ソファーでSMクラブの店長とおかまバーのママが談笑していました。
「酒屋の若旦那もいっしょに食べよ」ママがみたらし団子を差し出しました。
ここの人たちはみな私のことを「若旦那」と呼んでいました。私は叔父が経営する酒屋に勤めていたのですが、オーナーのKさんが勝手に跡継ぎだと思い込んだようでした。
3人でみたらし団子を頬張っていると、スズメという源氏名の女の子が客といっしょに店から出てきました。
釣り好きのKさんがスズメダイから取って付けた源氏名で、他にもヒラメとかウニといった名前の女の子がいました。
「ありがとうございましたー!先生また来てねー!」
スズメちゃんの元気な声が廊下に響き、先生と呼ばれた客は照れくさそうにぺこぺこと頭を下げながらエレベーターホールへと歩いていきました。
「あ~、クサかった~」顔をしかめながら店に戻るスズメちゃん。
消臭スプレーを手にまた廊下へ出てくると、エレベーターホール周辺を消臭し始めました。
すると、店の中から他の女の子たちの騒ぎ声が聞こえてきました。
「うわ~、めっちゃクサい!」「トイレまでクサくなってる!」そんな声とともに、数人の女の子たちが消臭スプレーを手に店内を行ったり来たりし始めたのです。
どうやら先ほどの先生と呼ばれていた客の口臭が異常なくらい強烈だったようで、接客したスズメちゃんだけでなく他の女の子たちまで我慢できず消臭スプレーを撒き始めたということでした。
スズメちゃん曰く、あの客は口臭が強烈なだけでなく、ディープキスをしたときに口の中から変な臭いの液体を出してきたことがあって、そのときは慌ててトイレに駆け込んだのだとか。
「あのオッサン、高校の地理の先生やって言うてたけど、あんな口臭で授業されたら教室がパニックになるやろ。先生なんてぜったいウソやわ!」
スズメちゃんはそう話していました。
店の女の子が客の噂話をしたり悪口を言ったりするのは日常茶飯事なのかもしれません。
デリヘルなどでは待機所が個室になっていて女の子どうしで話す機会がないとか、大部屋でいっしょになっても会話は少ないといった話を聞いたことがありますが、『R』では女の子どうしが待機中にペチャクチャおしゃべりしている光景をたびたび見かけました。
私は納品のときに店の厨房内へ入ることがよくあったのですが、すぐ横に女の子の待機スペースがあり、彼女たちの会話が筒抜けで、客の悪口を言っていることもありました。
どれも本人の前では言えないような内容ばかりでした。
客とオーナーが口論
たしか梅雨の時期だったと思います。店前のソファーでKさんや女の子数人としゃべっていると、ボーイが出てきて「お客さんがビールのガスが抜けてて不味いとクレームをつけてまして…」と困った顔をして言いました。
その当時『R』では、350ml缶の発泡酒をグラスに入れて提供していました。以前は生ビールをサーバーから注いでいたのですが、経費節減のためにKさんが缶の発泡酒に切り替えたのでした。
メニューにはちゃんと発泡酒と記載されてありました。店によっては生ビール(スーパードライ)と書いていても実際は韓国製の発泡酒や第三のビールを使っているところもあります。その点では『R』は明朗な店だったと言えます。
発泡酒だからビールよりもガス圧が弱く感じたのではないかと、Kさんがその客に説明したのですが、客は納得しませんでした。
だいぶ酔っている様子のその客はKさんに食ってかかり、Kさんもそれに応酬。激しい口論に発展してしまいました。
「気に入らんのやったら他所へ行けや!」
Kさんの怒鳴り声が店内から聞こえてきました。結局、Kさんの迫力に気圧された客はしゅんとなり、ボーイにつまみ出されてとぼとぼと帰って行ったのでした。
じつは前の客の残りもの
普段は営業時間前に納品に行くのですが、その日はたまたま追加の注文があり、夜9時を過ぎてから『R』へ配達に向かいました。
厨房の棚に焼酎やウイスキーを並べていると、ボーイが客に出すビールを取りに来ました。そのとき、私は思わず目を疑いました。
ボーイが冷蔵庫から出してきたのは、缶のプルトップが開いた発泡酒だったのです。それをグラスに注ぐと、足りない分は新たに缶を開けて継ぎ足したのでした。
つまり、前の客に出したときに余った分を次の客に出していたというわけです。
私はてっきり、350ml缶1本をそのままグラスに移し替えて出していると思っていたのですが、そうではなく、ちょっと小さめのビアグラス(280mlくらい)1杯分を出していたのでした。
「ビールのガスが抜けてて不味い」と言ってクレームをつけた客のことを思い出しました。あれは恐らく、前の客に出したときの残りを入れたためガスが抜けていたのだと思います。
私は見てはいけないものを見てしまった気がして、急いで納品を終え料金を受け取ると、その日は誰とも立ち話などせずに帰りました。
その後、ほとんど毎日のように納品に行くうち、色々なことがわかってきました。発泡酒のことだけでなく、焼酎やウイスキーを水で薄めて出していることも知ってしまいました。
焼酎やウイスキーは客の希望で「ストレート、ロック、水割り」を選べるようになっていたのですが、ストレートであってもすでに水で薄められた状態でしたから、ロックや水割りだとさらに薄くなっていたはずです。
出入りのヤクザが洒落にならないくらい怖かった
現在は暴対法の強化や暴力団排除条例の施行により、風俗店や水商売関係の店にケツ持ちのヤクザがいることは少なくなりましたが、私が酒屋の配達員として働いていた20年ほど前は、まだまだそういうことが普通にあった時代でした。
セクキャバ『R』にもやはり出入りのヤクザがいました。田村(仮名)という某指定暴力団の二次団体の幹部で、その当時40代前半くらいだったと思います。『R』の他にもいくつかのキャバクラやセクキャバにかかわっていて、自身でもスナックや韓国エステを経営していたようでした。
初めて田村に会ったとき、私は小便をちびりそうになったくらい怖かったのを覚えています。そんじょそこらのチンピラとは格の違う迫力がありました。田村が歩いてくると100mくらい離れていても殺気を感じました。
田村が歓楽街を練り歩けば、それまで賑やかな声を上げながら客引きをしていたホストやキャバクラの女の子たちは、みなピタリと話を止め、ビルの中へと隠れてしまいました。
いったいどんな人生を歩んできたら、あんなめらめらとした殺気を身にまとうまでになるのか…。私は絶対にこんな人物とは関わり合いになりたくないと思いました。
しかし、Kさんと親しくなり、『R』の女の子や近所のスナックのマスター、おかまバーのママたちとの付き合いが生まれると、そのうち田村とも関りを持つようになってしまいました。
あるとき田村から、その当時人気のあった入手困難なプレミアム焼酎を取り寄せてほしいと言われたことがありました。
「入ったら俺のとこ持ってこい」そう言い、田村は携帯番号を私に教えてきました。
しばらくして商品が入荷したのですが、私は田村のところへ行くのが嫌で、先輩従業員に配達を代わってくれと頼みました。
「なんでオレが行かなあかんねん。お前が注文を受けたんやろ」
先輩もヤクザの所なんか絶対に行きたくないと言い、私は仕方なく自分で田村の携帯に電話をかけたのでした。
「おう、そうか。そしたら明日の晩、『R』へ持ってきてくれ」田村は言いました。
私はちょっと安心しました。てっきり組事務所まで持ってこいと言われる気がしていたのです。『R』なら他にKさんや顔見知りの人たちがいるので、何かあってもフォローしてもらえるだろうと思いました。
結果的になんの問題も起きず、商品を渡してその場で支払をしてもらうことができたのでした。
ちなみに、領収書の宛名は組の名前ではなく、別の会社名を書かされました(おそらく組のフロント企業だと思います)。
「お前のその腕、引きちぎったってもええんやぞっ!」
セクキャバ『R』へ行くようになって一番怖い思いをしたのは、やはりあのときの事件です。
私は仕事終わりに店前のソファーでKさんらと談笑していました。その日はSMクラブの店長やおかまバーのママ、そして『R』の女の子数人もいて、いつもより賑やかでした。
ヤクザの田村も来ていて、スロットマシンの前で暇つぶししていました。
そのとき、『R』で人気ナンバー1のナギサという女の子がいきなり店から飛び出してきて、「お客さんがパンツ脱いで無理やり入れようとしてきた」と泣きそうな顔でKさんに訴えかけてきたのでした。
そのあとすぐにボーイも出てきて、「お客さんに注意したんですが、逆ギレされまして…」と言います。
Kさんが「俺が言うてきたるわ」と言って立ち上がろうとしたとき、それまでスロットマシンをいじっていた田村が腰を上げたのです。
「待て。俺が言う」そう言って店内へと入って行った田村。
じつはナギサというのは、田村がどこかから連れてきて『R』へ紹介した女の子だったのです。それで田村も何か思うところがあったのかもしれません。
店内から客が喚き散らす声が聞こえてきました。しかし、そのあとに田村の地鳴りのような野太い怒声が響き渡ると、一瞬にして静まり返りました。
客の男が店から転げ出てきました。茶髪で色付きレンズの眼鏡をかけたチンピラ風の男でした。ズボンとトランクスがずり落ちそうになっていて、半ケツを晒していました。
田村が出てきて、「本番やりたいんやったらソープでも行ってこい!」と男を怒鳴りつけました。
「やかましわいっ!ヤクザもんが何ぬかしとんじゃ、ボケっ!」
客の男が激しい口調で言い返したと思うと、田村がいきなり男の横っ面を殴りつけたのでした。「ボコっ」という音がして、色付き眼鏡が勢いよく飛び、顔をおさえてその場にくずおれたチンピラ男。
ソファーに座っていたKさん以外のメンバーはみな呆然とした顔で、その様子を見ていました。
「お前のその腕、引きちぎったってもええんやぞっ!」
田村は野太い怒声を浴びせると、その場に這いつくばっているチンピラの横っ腹に蹴りを入れました。男は低い呻き声を漏らし、ばたりとその場に倒れこんでしまいました。
私は恐怖のあまりソファーの上で置き物みたいに固まっていました。金玉も通常の半分以下の大きさまで縮み上がっていたと思います。
「もう、それくらいにしといたれや」
Kさんが苦笑いを浮かべながら言いました。田村は平然とした態度でエレベーターホールへと歩いて行ってしまいました。
「お兄さん、あんたもついてないのぉ」
周囲がしーんと静まり返る中、Kさんひとりだけが笑顔でした。
住む世界が違う
いちど、Kさんや『R』の女の子、スナックのマスターらと深夜にタチウオ釣りに行ったことがありました。現場に着くと、田村が来ていました。
田村は知り合いの不動産会社の人間といっしょに来ていて、私たちも彼らと並んで釣りをしました。
『R』の女の子ふたりはちょっと居心地悪そうにしていましたが、私は高価なプレミアム焼酎を購入してもらった手前、田村の存在をあからさまに避けるわけにもいきませんでした。
釣り糸を垂らしながら世間話をしてみると、田村は意外にも気さくな人物で、最初に会ったときみたいに殺気を感じさせることもありませんでした。
わりと感じのいい人なんだなあと、そのときは思いました。しかし、やはりこういう世界の人たちとは深く付き合うべきではないと思いました。
Kさんも含め、付き合ってみると感じのいい人かもしれませんが、自分とは住む世界が違う、生き方の違ういい人なのだと、私は自分自身に言い聞かせたのでした。